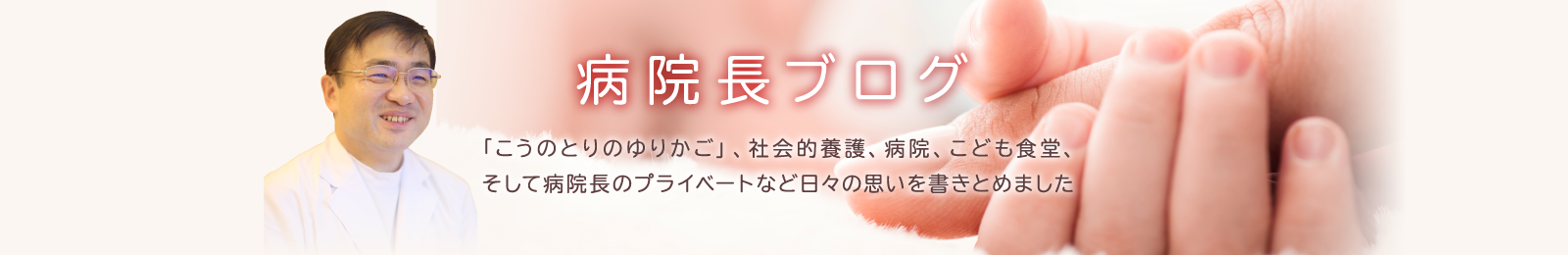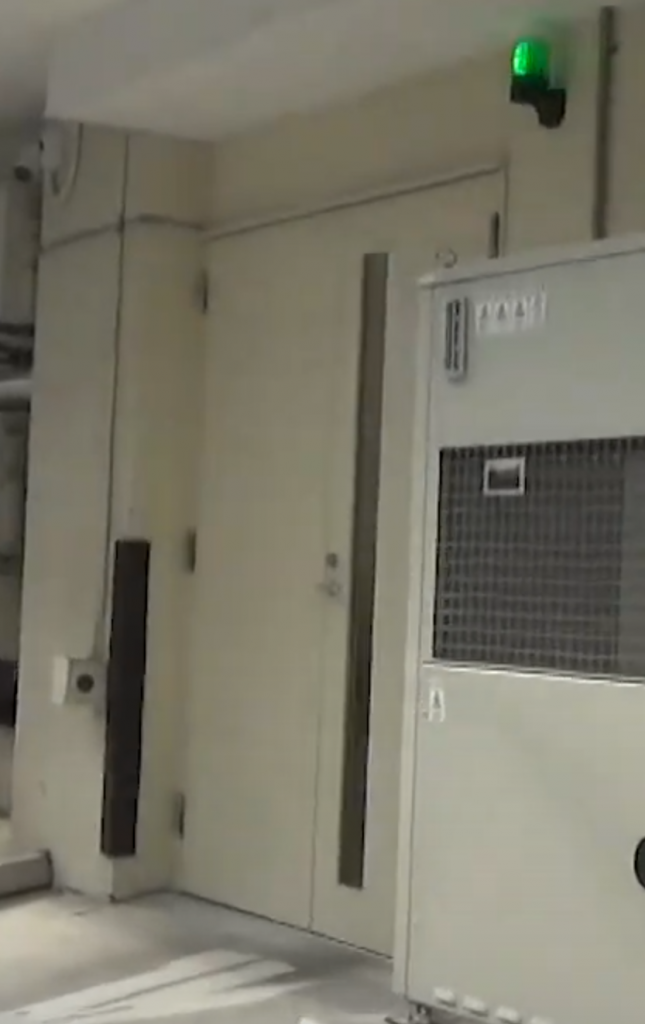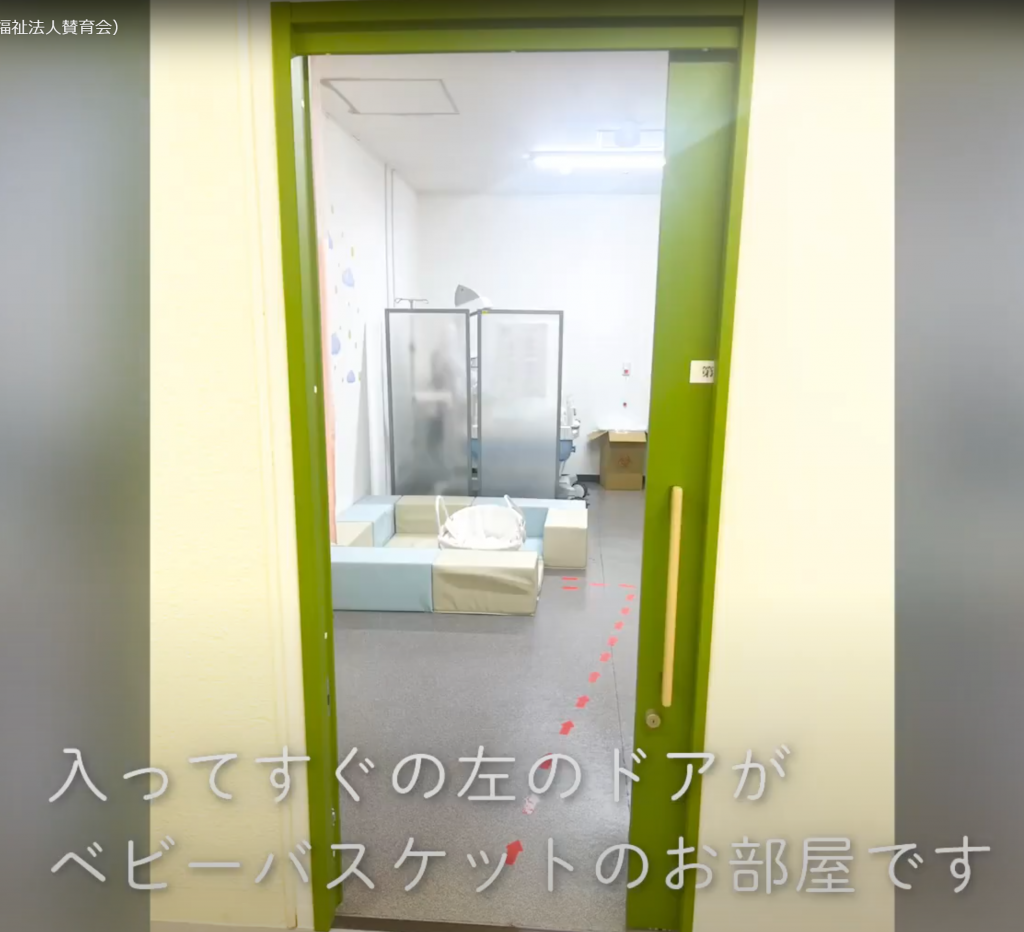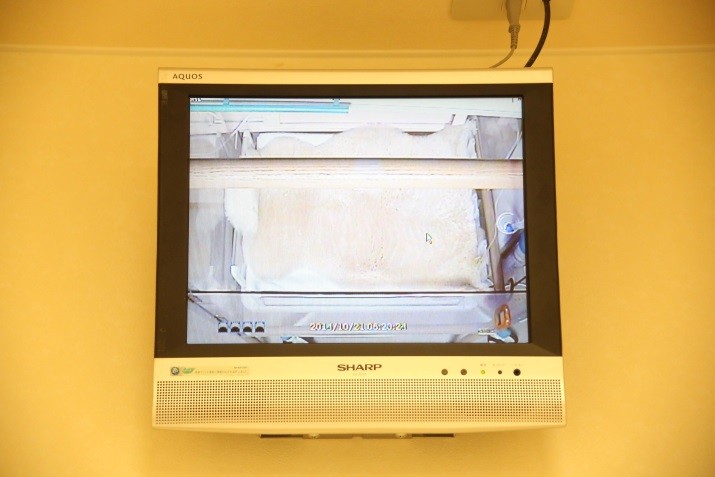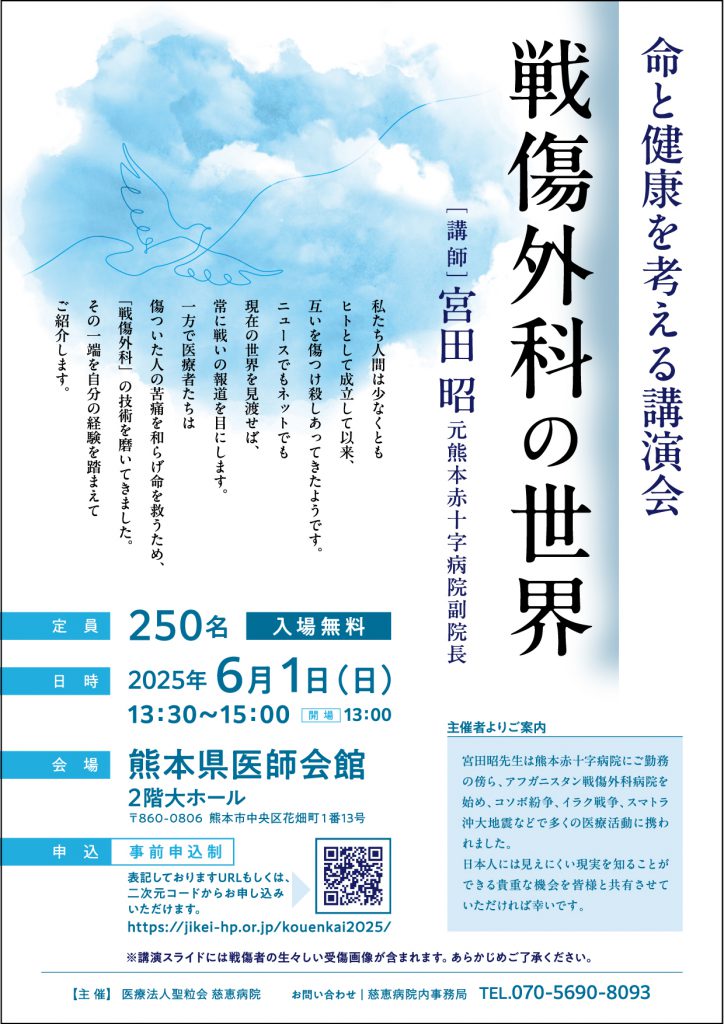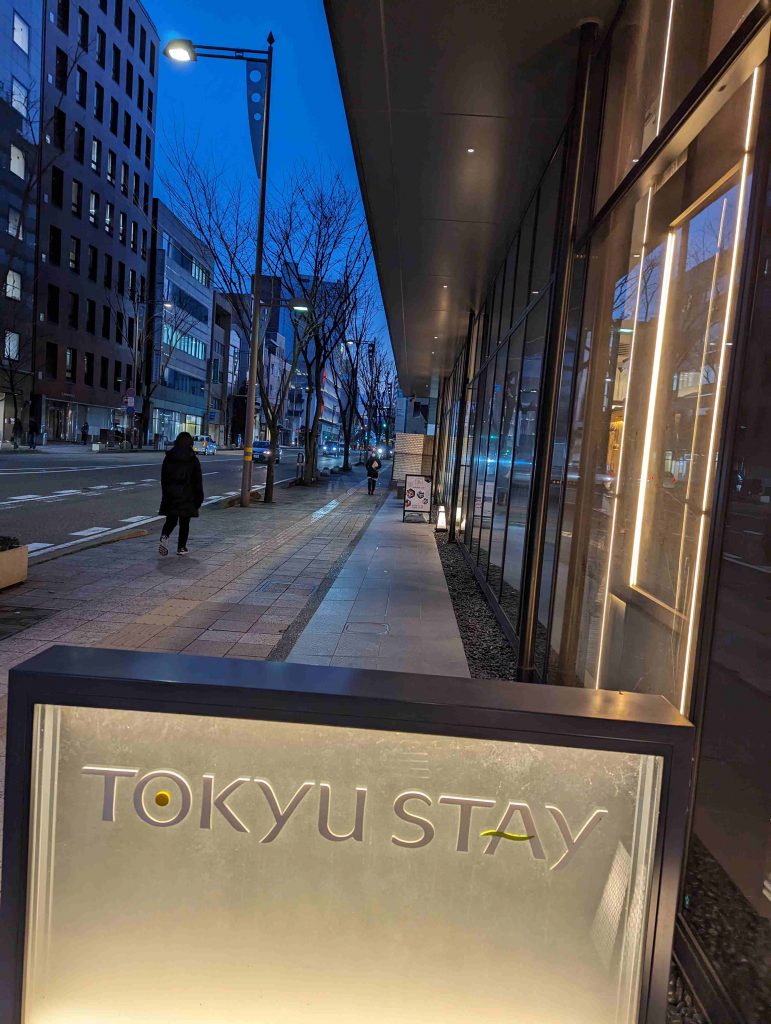宇宙人?
東京の賛育会病院が始めた有料の内密出産は驚きでした。ニュースを見て私が最初に思ったのは、「賛育会病院はどのような妊婦さんを想定しているのだろう?」でした。
私は有料内密出産を受け入れる女性に会ったことがありませんし、それをできる人がどんな人なのか思いつきません。私の中では「50万円を持っている女性」と「内密出産を求める女性」はどうしても結びつかないのです。誤解を恐れずに言わせてもらいますと宇宙人です。出会ったことはないけれど、もしもいるなら会ってみたい人です。
自然分娩50万 帝王切開80万
内密出産が有料ということは既に複数の報道機関が報じていますので間違いはないと思います。例えば令和7年3月31日に日本テレビは次のように報じています。
「内密出産の場合、帝王切開か普通分娩かで費用は異なるものの、約50万円ほどかかる費用は『原則本人負担』だということです。病院側は『話し合いの上でどのようにお金を払っていくか相談する』と述べました」
この情報の通りなら自然分娩で50万円、帝王切開で80~90万円かかる費用を出産した女性が自己負担することになります。健康保険に加入していて、かつ匿名でなければ出産一時金50万円が支給されますし帝王切開によるオーバー分も健康保険がカバーしてくれますが、匿名ではそのようなお金はもらえません。
有料は非現実的
そもそも50万円のお金を貯める能力を持つ人は内密出産のお世話にはなりません。有料では女性たちに「内密出産の看板はあるけれど使わないでね」と言っているようなものです。
慈恵病院は過去3年4ヶ月で48例の内密出産を経験しましたが、50万円を現金で用意できる女性は皆無でした。それどころか熊本に来る旅費すらなく、病院が旅費を送金して新幹線の切符を買ってもらったケースもありました。
日本は年間12万件の人工妊娠中絶が行われている国です。倫理的問題は別として、日本では予期しない・望まない妊娠の解決法として中絶は一般的ですから、50万円の蓄えがある人でしたら中絶を選択するでしょう。
東京からの問い合わせ5件
3月31日の発表以来、慈恵病院には東京在住の女性から5件の内密出産相談がありました。「東京で内密出産ができると知ったのですが、お金がなくて。熊本でできますか?」という訴えでした。
これらの案件について私は賛育会病院に電話やメールで問い合わせを行ったのですが、全く返事をいただけていません。
患者さんの困りごとの受け皿となるべき医療機関の姿勢として如何なものかと思います。せめて「対応できる」「対応できない」の返事を送るのが医療機関の責任ある姿だと思うのですが。
一方、慈恵病院で内密出産をした女性たちからは「ニュースで見たけれど有料の内密出産なんてムリです」と憤りの声が寄せられました。やはり有料内密出産は現実的ではありません。
収入はあるのにお金がない
お金を貯めるには稼ぐ能力だけでなく、お金を管理する能力が求められます。
かつて慈恵病院にたどり着いた女性の中には、夜の仕事で1ヶ月に80万円の収入を得ていた人もいましたが、手持ちのお金はほとんどありませんでした。お金を手に入れても、それを彼がいるホストクラブにつぎ込んでしまったからです。
小さい頃から人に愛されたり大事にされたりしたことがなかった女性が、女性を食い物にしているような男性に貢ぎ続けることがあります。搾取し暴力を振るう男性であっても、時々優しくして抱きしめてくれると女性はそれにすがり依存してしまいます。
お金を貯めるには「お金を遣わない自制心」や「自らの行動が招く結果ついての予測力」、「人を見定める目」などいくつかの能力が求められます。残念ながら内密出産を求める女性の中には、そのような能力に乏しい人が少なからずいます。
もちろん、その能力を持つ人もいましたが、学生さんを始め収入自体が少ない人にとっては50万円、90万円はとても手元に持てる金額ではありません。賛育会病院の関係者は「人生の一大事なら50万円くらい出せるだろう」と思っているのかもしれませんが、私に言わせれば孤立妊娠女性たちの実情を理解していない、「できる人」の言い分です。
分割払いも現実的ではない
先の報道記事には「話し合いの上でどのようにお金を払っていくか相談する」とありました。恐らく分割払いのことでしょう。
しかし収入が少ない人にとって50万円の借金を返すのは大変なことです。彼女たちの中には既にカードローンで破綻している人もいるわけですから、借金の返済には馴染みません。
病院が「借金取り」になってしまいますと、実母さんは病院にネガティブな感情を抱き音信不通になる恐れがあります。
生まれた赤ちゃんが将来自らの出自を知りたいと考えたとき、実母さんがそれに協力してくれるかどうかは重要です。実母さんはキーパーソンですから、子どもの出自を知る権利を尊重する観点からも実母さんと病院との関係悪化は避けたいところです。
職員もストレス
有料内密出産は医療の現場に立つ職員さんにもストレスです。内密出産では陣痛が始まった女性が、病院の窓口に飛び込むこともあります。医療者としては陣痛で苦しんでいる女性に「お金を払えますか?」とか「分割で払えますか?」などとお金の交渉をするのははばかられます。
とりあえずお金の話を抜きにして出産までこぎ着けるでしょう。しかし出産後にお金の話をするとき、女性側が「そんな話は聞いていない、知らなかった」と拒む可能性もあります。
今は東京の内密出産が始まって1ヶ月ですから有料内密出産がマスコミで取り上げられていますが、数ヶ月すればこの情報も埋没してしまいます。有料を知らずに助けを求める女性も出てくるでしょう。
内密出産は50万円のお金を払えない人ばかりが来る世界です。現場の職員さんが毎回お金の交渉をしなければならないストレスを抱えながら医療活動を行うのは問題です。
有料は世界初
このような事情から有料の内密出産は現実的ではありませんし好ましくありません。世界的にも有料の内密出産や匿名出産は例がありません。残念なことですが、有料内密出産は日本が生み出した世界初のシステムです。
海外の各国は内密出産が必要な女性たちの実情を分析し、本人から費用徴収することが現実的ではないと判断したのだと思います。自己負担ではシステムの存在意義を損なうことから公費負担になったのではないかと私は推察します。
内密出産の法制化がなされていない日本では公費負担はかないませんので、日本で内密出産を実施するには病院の費用負担は避けられません。
理解と覚悟が必要
私には奇異に映る有料内密出産ですが、その背景には賛育会病院の不安があると思います。東京で内密出産を行えば事例数は熊本の数倍になります。その費用負担を支えきれないのではないかという不安です。
それを乗り越えるには、まず新生児の遺棄や殺人の現実を知り内密出産の存在意義を理解する必要があります。
私は3年前まで女性たちに交通費を振り込むことを躊躇していました。しかし裁判を通じて遺棄・殺人事件の悲惨な現実を知るようになってからは、「50万円で赤ちゃんの命や健康を買えるならば安いものだ」と思えるようになってきました。
優しさとか正義感だけでは日本の内密出産は運営できません。諸外国のような法整備がなされていないない日本の内密出産は世界で最も実施困難なものです。運営者には実情を理解し自ら負担する覚悟が求められます。
受け入れられるサービスを
社会福祉のサービスは利用者が受け入れられるものでなければ無意味です。利用者に合ったものを用意するのが提供者の責務です。利用者がその提案を拒絶したときに、「それではしようがないですね」と言ってしまうようでは支援ではありません。
もしも受け入れられないものばかりを提案する「支援者」だとすれば、それは支援者ではなく、自己満足や偽善とのそしりを受けても仕方がありません。残念なことですが孤立妊産婦支援の現場を見渡しますと、サービスの提供者が利用者にとって受け入れることのできない選択肢を提示する事態が散発します。
無料と宣言してほしい
賛育会病院のホームページには「キリスト教の『隣人愛』の精神に基づいた…」と理念がうたわれています。
私は洗礼を受けていませんし、聖書も1ページ読んだだけで脱落しました。しかしネットで調べて隣人が「隣の人」ではなく「困っている人」「助けを求めている人」「弱く貧しい人」を意味することもあると知りました。
赤ちゃんポストや内密出産の世界では孤立妊産婦こそが隣人だと思います。私は賛育会病院には堂々と「内密出産でお金はいただきません」と宣言していただきたいのです。それが孤立妊産婦には福音だと思います。