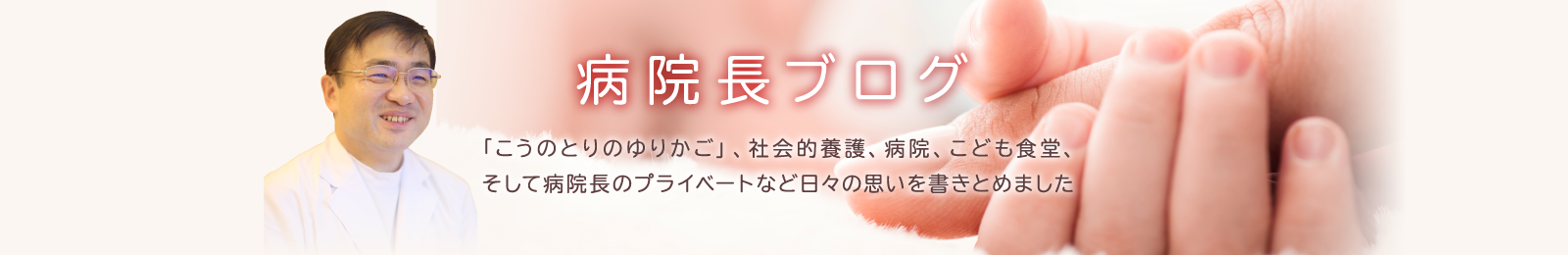思わぬ妊娠に困った女子高校生が慈恵病院に相談の電話をくれたことがあります。
すでに彼女のお腹はふっくらしかけていましたが、親御さんはご存知ないとの事でした。
本人は、「親には絶対言えない」と言います。厳格なお父様の家庭で育った彼女には打ち明ける勇気がありませんでした。そこを説得して、親御さんを含めた3者面談をする事になりました。
その場でお父様がおっしゃったのは、「うちの娘には責任を取って育てさせます」との言葉でした。赤ちゃんの父親にあたる人物は同級生の男子高校生でしたが、すでに別れていて、生まれてくる赤ちゃんを育てる気持ちはありません。彼女にも進学したい気持ちが強く、育児には消極的でした。私はこの状況を心配しました。確かに、赤ちゃんの親となった責任として赤ちゃんを育てていくうちに、赤ちゃんに愛情を持てるかもしれません。しかし、そうでないケースも少なくありません。慈恵病院の電話相談には、「赤ちゃんを愛せない」「赤ちゃんが可愛くない」「育てるのが辛いので赤ちゃんポストに預けたい」と訴える女性の声が寄せられます。
「我が子を可愛くないと思わない母親はいない」と言う人がいますが、このような『母性神話』的な考えから外れるケースが多々あるのです。
もちろん、高校生に子育てができないと言っているのではありません。学校を退学して子育てをした高校生はいます。また少ないケースですが、学校に通いながら、親御さんに手伝ってもらい赤ちゃんを育てた学生さんもいました。彼女たちに共通するのは、赤ちゃんを育てたいという意欲です。イヤイヤながらではありませんでした。
高校を卒業して就職や進学をしていく同級生達が、コンパ、デート、旅行などを楽しんでいる時期に、子育て中心の生活を送るのには一定の覚悟が要ります。見方によっては、子育ては地味で忍耐を必要とする活動です。親となった責任をとって育てたものの、イヤイヤながら育てていては、いずれ我が子への言動に影響が出てきます。明らかな虐待がなくても、子どもが傷つく言葉が口をついて出てきかねません。「産みの親」「実の親」に育てられているとは言え、親にとって「お荷物」となってしまったら、むしろ子どもが可哀そうです。
先のケースではカウンセリングを重ねた結果、赤ちゃんを特別養子縁組に託す事になりました。女子高校生の親御さんも、本人にとって子育てが予想以上に負担の大きいことを理解なさったようです。
この高校生が出産した時、養子縁組を希望するご夫婦が病院に駆けつけて来ましたが、赤ちゃんと対面した時にご夫婦で涙を流して喜ばれました。
赤ちゃんにとってベストの選択は「実の親が責任を持って、愛情深く育てる」という事かもしれませんので、特別養子縁組は次善の策になります。しかし、このケースでは現実的にはベストの選択だったと思います。ご夫婦の涙を見て、そう思いました。